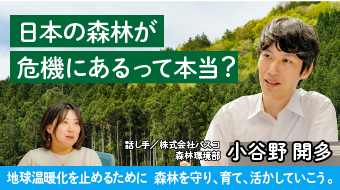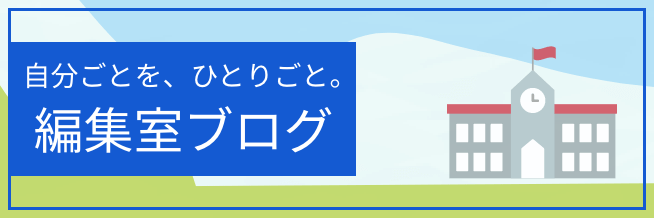私たちの食卓を豊かにしてくれる農業の未来は?

お米や野菜が買えなくなる?
無関心ではいられない日本の農業の問題とは。
2024年夏、小売店の店頭からお米が消えました。2025年に入っても品不足や値段の高止まりは続いており、政府の備蓄米の放出など、連日ニュースになっています。また、お米だけでなく、キャベツやレタス、白菜など身近な野菜の価格も不安定になっています。「今後、お米や野菜が手に入らなくなってしまうのでは」と不安に思う人も多いのでは? なぜこうした状況が起きてしまうのか、そして、日本の農業は今どのような問題を抱えているのか、農業情報課の小林沙綾さんにうかがいました。
プロフィール

話し手 小林 沙綾
株式会社パスコ 東日本事業部 社会情報部 農業情報課
岩手大学大学院にて農学生命を専攻。2014年に新卒でパスコに入社後、一貫して自治体の農業分野に関わる支援業務に携わる。

聞き手 樋口 沙紀子
地球の学校 編集室
食卓に異変。農作物の未来はいったいどうなる?

最近、スーパーに並ぶ農作物の種類や量、価格が不安定になっていると感じます。これからも安心しておいしい食事を楽しみたいのですが、正直不安です。いったい何が起こっているのでしょうか?

たしかに、スーパーでいつもは置いてある野菜が品切れになっていることが増えましたし、農作物の価格変動も激しくなっていますね。
たとえばお米の場合、5㎏の2025年3月時点での店頭平均価格が4,172円と、去年の同じ時期の2倍以上になっています。
たとえばお米の場合、5㎏の2025年3月時点での店頭平均価格が4,172円と、去年の同じ時期の2倍以上になっています。

頭が痛いです。

このお米の価格の大幅な値上がりは、2023年夏の異常な暑さや水不足の影響により、お米に白濁などの品質低下が起きたことで出荷量が減り、翌2024年に出回る量が不足したことが原因の一つと考えられています。

2年前の異常気象の影響が続いているということですか?

はい。また、コロナ禍が落ち着き、外食する人や海外からのインバウンドで和食を楽しむ人が増え、お米の消費も増加傾向になりました。そうしたなか、2024年8月、南海トラフ地震の臨時情報が出て、普段以上にお米を備蓄する家庭が増えたことで、米不足に拍車がかかりました。さらに、ガソリン価格の高騰や人手不足による流通の停滞、一部の業者による売り渋りや買い占めなども原因という声もあります。
「令和の米騒動」と呼ばれる米不足と価格高騰は、さまざまな要因が重なって起きたと考えられます。
「令和の米騒動」と呼ばれる米不足と価格高騰は、さまざまな要因が重なって起きたと考えられます。

農業従事者減少と放棄地増加で、ますます深刻な事態に

原因はひとつではなく、複合的なものなんですね。
じつは、私の実家近くは田園風景に囲まれた田舎なのですが、手入れがされていない田んぼや畑を目にすることがありますし、跡継ぎがいなくて農家をやめたという話もよく聞くんです。お米や野菜をつくる人自体が減っていると感じるのですが、そもそも日本の農業はいまどういう状況にあるのですか?
じつは、私の実家近くは田園風景に囲まれた田舎なのですが、手入れがされていない田んぼや畑を目にすることがありますし、跡継ぎがいなくて農家をやめたという話もよく聞くんです。お米や野菜をつくる人自体が減っていると感じるのですが、そもそも日本の農業はいまどういう状況にあるのですか?

いま、農業に携わる人の数は減少する一方です。専業農家数は、2024年の全国推計値で約111万人と、5年前に比べて35%以上も減少しました。また、平均年齢は69.2歳と高齢化も進んでいます。


70歳近い平均年齢とは驚きですね。

はい。その影響もあり耕作放棄地も増えています。少し前のデータですが、2015年時点の全国の耕作放棄地の面積は42万haと、滋賀県の面積とほぼ同じ広さになっています。

それだけの広さの農地が使われていないなんて、もったいない気がします。

耕作放棄地になるのは、山間部にある田んぼや畑など、比較的利便性が低い農地が多いのですが、それだけが理由ではありません。そもそも、農作物の収穫量や品質は天候に左右されやすく、農家の収入は必ずしも安定しません。
先ほどお米の値段が1年前の2倍になった、という話をしましたが、米農家からは「そもそもこれまでが安すぎた。今回の価格上昇でようやく利益が出るようになった」という声も聞かれます。それくらいぎりぎりの経営になっているところも多いのです。
先ほどお米の値段が1年前の2倍になった、という話をしましたが、米農家からは「そもそもこれまでが安すぎた。今回の価格上昇でようやく利益が出るようになった」という声も聞かれます。それくらいぎりぎりの経営になっているところも多いのです。


思った以上に深刻な状況なんですね。

また、自然相手の仕事は、手間と労力がかかります。天候だけでなく、病虫害や鳥獣害にも気を配らなくてはなりません。そして、経験から蓄えられた知識や技術を伝承するには時間も必要で、後継者の育成も簡単ではありません。「先祖代々の田んぼと畑があるから続けてきたが、農業は自分の代で終わりにしたい」と考えている農家の方も決して少なくないのが実情だと思います。
低い日本の食料自給率。輸入への依存は大丈夫?

日本の農業がたくさんの課題を抱えていることがわかりました。私たちの食生活に欠かせないお米や野菜を作ってくれる人がこのまま減り続けたら、輸入に頼るしかないのでしょうか?

日本の2023年度の食料自給率は、カロリーベースで38%に留まっています。カロリーベースとは食料自給率をカロリーで計算する方法です。足りない分は海外から輸入しているわけですが、最近は世界的にも異常気象が続いていて、これからも安定して食料を輸入できる保証はありません。

輸入できるから安心、というわけでもないのですね。

そうなんです。さらに、ロシアのウクライナ侵攻で小麦の価格が高騰したように、国際情勢にも大きく左右されます。そうした影響をなるべく抑え、国民全体の安定した食生活を守るためにも、日本の食料自給率を高めていくことは長年の課題になっています。

未来の食生活を守っていくために、どんな対策が取られているのでしょうか?

まず国は「食料・農業・農村基本法」という法律を定めて、食生活の安定や、農業の持続的な発展、農村の振興などを図っています。また「農業振興地域の整備に関する法律」 をつくり、各市町村がその法律に基づいて、農業の振興を図るべき農地を農振農用地として指定し、優良農地を確保しています。

優良農地、ですか。単純に条件が良いというわけではない?

農振農用地に指定されることで、農家は税の軽減や交付金、災害時の支援など各種の優遇措置が受けられるようになり、農業が続けやすくなります。また、農振農用地の指定は、優良農地がむやみに宅地などに転用されないように規制をかける役割も担っています。
農地が耕作放棄地になってしまうのを防ぐために、「農地中間管理機構(農地バンク)」を通じて、耕作が難しくなった農地を希望者に貸し出す支援なども行っています。
農地が耕作放棄地になってしまうのを防ぐために、「農地中間管理機構(農地バンク)」を通じて、耕作が難しくなった農地を希望者に貸し出す支援なども行っています。

農地を守るための切り札は「6次産業化」

法律や制度で農地を守っているんですね。そのほかにも、農作物の安定供給を実現するために、どのような取り組みが行われているのでしょうか?

そもそも安定供給というには、量・品質・価格のバランスが大切です。安全でおいしい品質を保ちながら、つねに一定かつ十分な量を確保し、しかも適正な価格で提供していくことが求められます。その取り組みの一例として「農産物のブランド化」があります。
たとえば「ブランド米」の開発です。各地域で食味や旨味などでの独自性を出した新しいお米の開発が進んでいます。こうした取り組みは、品質向上だけでなく、従来よりも安定した収穫量の確保にもつながります。
たとえば「ブランド米」の開発です。各地域で食味や旨味などでの独自性を出した新しいお米の開発が進んでいます。こうした取り組みは、品質向上だけでなく、従来よりも安定した収穫量の確保にもつながります。


ブランド化をすることで、消費者も安心して購入できるし、選ぶ楽しみもできますね。

また、農業の持続的な発展に向けては、「6次産業化」があります。これは、1次産業で生産した農産物を、2次産業である加工や製造を行い、3次産業である流通や販売までを一貫して手掛ける取り組みのことです。

1次、2次、3次を全部掛け合わせて、6次産業ですね。

そうです。たとえば、果物農家が自分でジャムをつくり、ネットやSNSを利用してPRし、直接消費者に販売する、といった手法は、6次産業化の一例です。
ほかにも、「農家レストラン」を開業して地元以外からも人を呼び込み、農産物を味わってもらいながら農村の活性化を図るなど、さまざまな取り組みが行われています。
ほかにも、「農家レストラン」を開業して地元以外からも人を呼び込み、農産物を味わってもらいながら農村の活性化を図るなど、さまざまな取り組みが行われています。

少し傷のついた果物や規格外のサイズの野菜も、付加価値をつけて売り出せる、ということですね!
農業の未来を拓く! スマート農業

農家の方々も、時代に合わせた取り組みを行なっているんですね。でも、高齢化や後継者不足など、すぐには解決が難しい課題もありますよね。そんな状況で未来の農業をより良くしていくには、どんな方法があるのでしょうか?

他の産業にも共通しますが、生産性の向上や効率化は農業の発展のカギになると思います。その点でいま注目されているのが「スマート農業」です。ロボット技術や情報通信技術(ICT)、AIなどのテクノロジーを活用して、農作業の省力化や効率化を図り、農作物の品質も向上させる取り組みです。

具体的にどういうものでしょうか?

わかりやすい例でいえば、ドローンによる農薬散布や、自動運転の農業機械などですね。こうした技術の活用で、農作業にかかる人手や負担を大きく軽減し、生産性を高めます。北海道などの大規模な農地では、自動操舵システム付きトラクターなどの導入が進んでいます。


なるほど。効率化はイメージできましたが、ICTでどうやって品質を向上させるのでしょうか?

たとえば、お米。衛星・航空機やドローンで田んぼを上空から撮影した画像を、ICTを使って解析することで、稲の成育状況がわかります。生育が遅れているところにだけ追加で肥料を与える、といったことが可能になり、お米の品質向上や収穫量の安定化につながります。


そんなことまでできるんですか!

また、レタスやミニトマトなどを屋内で人工的に制御して栽培する場合は、日照や温湿度などの栽培環境や与える水や肥料の量をICTで管理して、品質・収穫量の一定化に取り組んでいます。そして、蓄積したデータを活用して、どこでも、誰でも、農作物の生産に参入することが可能になります。

ICTの活用で、上手な農作物のつくりかたをデータ化して、若い世代へノウハウを引き継ぐことができたら素晴らしいですね。

そうですね。さらに、こうした技術を活用することで、日本の農産物を海外に輸出・販売しやすくなることも期待できます。日本の農産物は、果物などを中心に、おいしいと海外でも人気です。国内以外の販路を開拓していくことは、日本の農業にとってプラスになると思います。
農業が守る、日本の食と美しい景観

スマート農業の普及や、海外展開がもっと広まれば、若い世代で農業に関心を持つ人も増えると思います。日本の農業の未来に希望が持てるようになる気がします。

そうですね。農業を守ることは、食料の確保だけが目的ではありません。農業は、さまざまな環境や社会的な役割を果たしていて、多面的な機能を持っているんです。

農業の多面的な機能、ですか。

たとえば田んぼは、大雨の際に雨水を一時的に貯めることで、下流域の洪水被害を低減する役割を担っています。また、そこにはさまざまな生き物が暮らし、豊かな生態系をつくっています。そして、周囲の自然と一体となって、心安らぐ美しい農村の景色を形作っています。それは、農村に暮らす人たちだけでなく、日本全体の宝物と言っていいと思います。
農業を守ることは、私たち全員の暮らしと環境を守ることにつながることを、ぜひ理解していただきたいですね。
農業を守ることは、私たち全員の暮らしと環境を守ることにつながることを、ぜひ理解していただきたいですね。


日本の美しい風景を維持し、未来に受け継いでいくためにも、農業はとても大切だということがよくわかりました。そして、食料の安定供給だけでなく、私たちの生活にさまざまなところでかかわりがあることも新たな発見です。
お話をうかがって、今度帰省した時、地元の風景への感じ方が変わるような気がします。
日本に暮らす一人として、農業にもっと関心を持ち、できる支援をしていきたいと思います。今日はありがとうございました。
お話をうかがって、今度帰省した時、地元の風景への感じ方が変わるような気がします。
日本に暮らす一人として、農業にもっと関心を持ち、できる支援をしていきたいと思います。今日はありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。
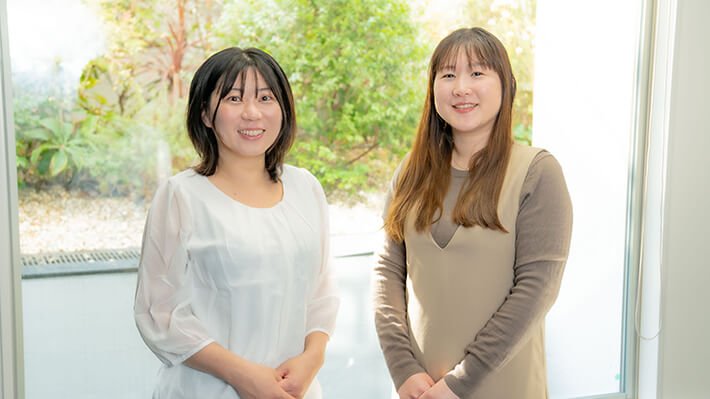
![脱炭素社会を実現するには? [後編]](https://geoschool.pasco.co.jp/assets_c/2_kou_thumbnail_250701_3.jpg)
![脱炭素社会を実現するには? [前編]](https://geoschool.pasco.co.jp/assets_c/1_zen_thumbnail_250701.jpg)