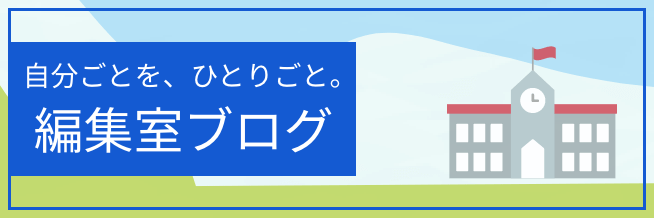私たちの生活を支える 「生物多様性」って何?
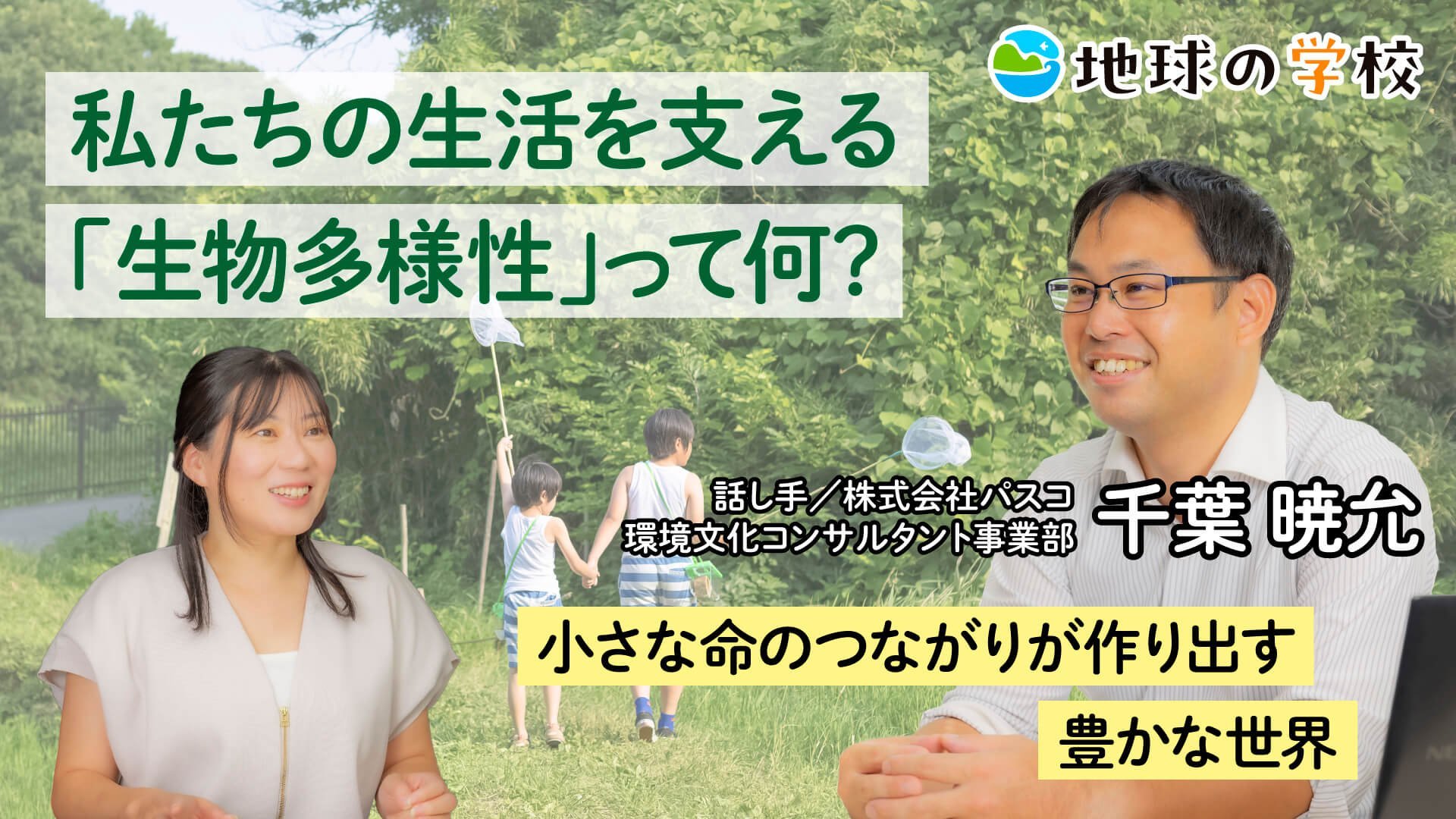
私たちの未来を支える「生物多様性」とは?
私たちの生活は実は見えないところで様々な生き物たちに支えられています。しかし、その生き物たちが今、危機に瀕しているとしたら……?
この貴重な自然の恵みを科学的に調査して未来に受け継いでいくために、どのような技術が活用されているのでしょうか。環境文化コンサルタント事業部の千葉暁允さんにお話をうかがいました。
「たくさんの種類の生き物がいる」だけじゃない! 3つの多様性とは

最近、「生物多様性」という言葉を聞くことが多くなりました。でも、意味をちゃんと理解できていません。どういう意味なのでしょうか?

生物多様性の定義は大きく3つに分かれます。
1つ目が「生態系の多様性」で、森や海、川といった生物が生息する多様な環境の存在です。
2つ目が「種の多様性」で、哺乳類、鳥類、魚類、昆虫類など、いろんな種類の生き物がいることですね。
そして3つ目が「遺伝子の多様性」で、同じ種の中でも個体ごとに個性がある、その多様性です。人間でも顔の形や目の形が違うように、動物にも個性があります。
この3つをひっくるめて生物多様性と呼んでいます。
1つ目が「生態系の多様性」で、森や海、川といった生物が生息する多様な環境の存在です。
2つ目が「種の多様性」で、哺乳類、鳥類、魚類、昆虫類など、いろんな種類の生き物がいることですね。
そして3つ目が「遺伝子の多様性」で、同じ種の中でも個体ごとに個性がある、その多様性です。人間でも顔の形や目の形が違うように、動物にも個性があります。
この3つをひっくるめて生物多様性と呼んでいます。

そもそも生物多様性という言葉はいつ頃から使われ始めたのでしょうか?

1980年代頃から自然環境の学者や環境保護団体の間で使われ始めたようです。日本では、1970年代の公害・環境問題への注目を背景に、徐々に広まってきました。そして、1992年のリオ地球サミットで生物多様性条約が採択され、国際的にも重要性が認識されるようになったのです。

そんなに前からある言葉なのに、なぜ今注目されているのでしょうか?

一番の要因は、絶滅が危惧される生物種が急増していることです。IUCN(国際自然保護連合)作成の絶滅危惧種レッドリストには、2024年時点で約4万種が掲載されています。日本でも環境省のレッドリスト(第4次レッドリスト改訂版)で、3,700以上の種が絶滅の危機にあると評価されています。
原因は主に3つあります。まず気温上昇や異常気象による生態系バランスの崩れ。次に人間の開発による生息・生育環境の消失。そして、外来種の影響なども含めた人間活動全般による環境変化です。
つまり、世界中で「保全に力を入れていかないと、本当にまずい」という段階に来てしまったということなのです。
原因は主に3つあります。まず気温上昇や異常気象による生態系バランスの崩れ。次に人間の開発による生息・生育環境の消失。そして、外来種の影響なども含めた人間活動全般による環境変化です。
つまり、世界中で「保全に力を入れていかないと、本当にまずい」という段階に来てしまったということなのです。

知らないうちに支えられていた、私たちの日常生活

絶滅のおそれがある生物がそんなに多いなんて驚きました。でも、なぜ保全しないといけないのでしょうか? そして、そのことと私たちの生活がどんな風に繋がっているのでしょう?

実は、私たちの生活は生物多様性によって支えられているといっても過言ではありません。
たとえば、私たちが日々口にする野菜や果物、魚や肉などの食糧は、様々な生き物の働きで得られます。ミツバチが花粉を運ぶことで果物や野菜が育ちますし、土の中の昆虫や微生物がいることで、栄養のある土が維持され作物を育てられます。
さらに、生物多様性が豊かな森や海は、快適な地球環境と健全な生態系を保つ役割を担っています。
多様な生物が互いに支え合うことで、自然界のバランスが維持され、地球全体の環境が安定しているのです。
その結果として、防災面でも大きな恩恵があります。針葉樹と広葉樹は異なる根の張り方をするため、多様な樹木がある森は土壌がしっかり固められて、土砂崩れや洪水を防ぎます。都市部でも公園や緑地の植物が木陰を作って涼しさを生み、ヒートアイランド現象(都市部が周辺地域より高温になる現象)を軽減しています。
さらに、文化的な面でも利点があります。豊かな自然は森林浴や自然散策などを通してストレスを軽減し、心を落ち着かせます。
松尾芭蕉の有名な俳句「古池や蛙飛び込む水の音」が描いているように、古くから日本で親しまれてきた情緒ある風景があるのも、この生物多様性のおかげです。
たとえば、私たちが日々口にする野菜や果物、魚や肉などの食糧は、様々な生き物の働きで得られます。ミツバチが花粉を運ぶことで果物や野菜が育ちますし、土の中の昆虫や微生物がいることで、栄養のある土が維持され作物を育てられます。
さらに、生物多様性が豊かな森や海は、快適な地球環境と健全な生態系を保つ役割を担っています。
多様な生物が互いに支え合うことで、自然界のバランスが維持され、地球全体の環境が安定しているのです。
その結果として、防災面でも大きな恩恵があります。針葉樹と広葉樹は異なる根の張り方をするため、多様な樹木がある森は土壌がしっかり固められて、土砂崩れや洪水を防ぎます。都市部でも公園や緑地の植物が木陰を作って涼しさを生み、ヒートアイランド現象(都市部が周辺地域より高温になる現象)を軽減しています。
さらに、文化的な面でも利点があります。豊かな自然は森林浴や自然散策などを通してストレスを軽減し、心を落ち着かせます。
松尾芭蕉の有名な俳句「古池や蛙飛び込む水の音」が描いているように、古くから日本で親しまれてきた情緒ある風景があるのも、この生物多様性のおかげです。

「生物多様性」を守るために必要なのは、現状の見える化

そういうことなのですね! 大切さを実感しました。その生物多様性を守るために、どうしたらいいでしょうか?

大切なのは、現状を正しく把握することです。生物多様性という言葉の持つ意味は非常に広く、様々な要素が複雑に絡み合っています。そこでまず、どこで何が起きているかを見える化しどんな影響があるのか、実態を把握することが重要です。
そのためには、肌感覚ではなく科学的な根拠をもとに判断できるように、しっかりとしたデータを取得し、蓄積する必要があります。また、生物や地域によって環境条件が異なるので、種や地域特性に合わせた調査計画が不可欠です。
そのためには、肌感覚ではなく科学的な根拠をもとに判断できるように、しっかりとしたデータを取得し、蓄積する必要があります。また、生物や地域によって環境条件が異なるので、種や地域特性に合わせた調査計画が不可欠です。

どんなふうに生物の現状を把握しているのでしょうか?

たとえば、離れた場所からセンサーを使って情報を取得するリモートセンシング技術や位置情報技術で、農作物の生育状況を把握したり、航空レーザーによる測量で3Dデータを取得したり、森林資源や植生・地形データを収集するなど、様々な調査手法を活用しています。
これらの調査をもとに、人と自然の共生を支える基盤作りにつながる「環境アセスメント」手続きを支援しています。
これらの調査をもとに、人と自然の共生を支える基盤作りにつながる「環境アセスメント」手続きを支援しています。
開発と環境の架け橋となる「環境アセスメント」とは

「環境アセスメント」手続きとは、どういうものですか?

「環境アセスメント」手続きとは、開発事業の内容を決めるにあたって、環境にどのような影響を及ぼすかをあらかじめ事業者自らが調査・予測・評価し、その結果を公表して一般の方々や地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
開発が環境に影響を及ぼすと考えられる場合は、適切な保全策を検討・実施することで、事業が環境の保全に十分に配慮して行う必要があります。規模が大きく、環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業は、法律や自治体の条例で手続きの実施が定められており、こうした一連の環境アセスメント手続きを支援するのが私たちの役割です。
開発が環境に影響を及ぼすと考えられる場合は、適切な保全策を検討・実施することで、事業が環境の保全に十分に配慮して行う必要があります。規模が大きく、環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業は、法律や自治体の条例で手続きの実施が定められており、こうした一連の環境アセスメント手続きを支援するのが私たちの役割です。

実際の調査はどのように行われるのですか?

たとえば、動植物では哺乳類のうちネズミ類の生息状況を調べるための「トラップ調査」、河川や水路で漁具を用いて魚を捕獲する「魚類調査」、陸産貝類の生息状況や気温・湿度・樹冠の隙間から差し込む光量を調べる「生息環境の調査」を実施しています。
調査は、渡り鳥のように季節によって生息する種が変わったり、繁殖期が限られている動植物もいますから、調査は一般的には四季を通じて行います。
調査は、渡り鳥のように季節によって生息する種が変わったり、繁殖期が限られている動植物もいますから、調査は一般的には四季を通じて行います。



調査結果によっては、当初の開発計画が変更されることもあるのでしょうか?

調査結果から、生物多様性を含む環境に大きな影響があると判断された場合は、まず事業の影響を回避するために、事業計画や改変範囲の見直しを検討します。どうしても回避できない場合は、影響を低減させる措置を検討します。
たとえば、オオタカなどの猛禽類であれば、繁殖期を避けた工事計画にすることや、営巣地から離れた場所から工事を開始して、作業騒音や作業員の存在に徐々に慣らしていく(コンディショニング)といった細やかな配慮を行います。
さらに、どうしても影響が避けられない、たとえば開発によって巣がなくなってしまう場合は、別の場所に代わりの人工巣を用意するという対策を講じます。開発と環境、人と自然の共存を探ることは、私たちの大切な仕事です。
たとえば、オオタカなどの猛禽類であれば、繁殖期を避けた工事計画にすることや、営巣地から離れた場所から工事を開始して、作業騒音や作業員の存在に徐々に慣らしていく(コンディショニング)といった細やかな配慮を行います。
さらに、どうしても影響が避けられない、たとえば開発によって巣がなくなってしまう場合は、別の場所に代わりの人工巣を用意するという対策を講じます。開発と環境、人と自然の共存を探ることは、私たちの大切な仕事です。
海の上でも活躍! AIを活用した洋上の生物調査

自然との共生を目指した開発といえば、洋上風力発電も思い浮かびますが、そこでも生物への影響を調査しているんですよね?

はい。洋上風力発電の開発では、事業開始前に海上を飛翔する鳥類への影響を調査しています。これまでは船舶での目視確認が主でしたが、見える範囲に限界があることや、海象条件が悪いと調査ができない、といった課題がありました。
そこで、センシング技術を活用して、調査の効率化や高度化を目指した研究を進めています。航空機から撮影した写真をAIで解析して鳥類を抽出するとともに、空間情報から飛翔高度を取得して、事業計画地や周辺海域を利用する鳥類の状況を把握する技術開発を進めています。
こういった技術を導入することで、従来の調査では確認できなかった、新たな種や活動が見つかるかもしれません。
そこで、センシング技術を活用して、調査の効率化や高度化を目指した研究を進めています。航空機から撮影した写真をAIで解析して鳥類を抽出するとともに、空間情報から飛翔高度を取得して、事業計画地や周辺海域を利用する鳥類の状況を把握する技術開発を進めています。
こういった技術を導入することで、従来の調査では確認できなかった、新たな種や活動が見つかるかもしれません。
生活のすぐ隣に広がる、かけがえのない命の連鎖

貴重な生物多様性を守り、受け継いでいくために、私たち個人にできることはありますか?

まずは身の回りの自然に目を向けてみてください。近くの公園の花や緑を眺めたり、見かける鳥の種類を覚えたり、道端の植物に注意を向けたり。身近な自然を楽しむことが、第一歩になると思います。
そのうえで、ゴミを減らすなど、環境破壊につながるような消費を避けるのが有効です。「森林認証」や「海洋認証」を取得した商品を選ぶのも、一つの方法です。少し高価になるかもしれませんが、そうした商品を選ぶ消費者が増えることが、生物多様性を守ることにつながると思います。
また、飼いはじめたペットは自然に放さないこと。最期まで責任を持って、命を大切にしましょう。
自治体やボランティアが主催する自然観察会に参加するのも良いでしょう。観察結果が自治体や環境省のデータとして活用される場合もありますから、実際の保全活動にも役立ちます。
そのうえで、ゴミを減らすなど、環境破壊につながるような消費を避けるのが有効です。「森林認証」や「海洋認証」を取得した商品を選ぶのも、一つの方法です。少し高価になるかもしれませんが、そうした商品を選ぶ消費者が増えることが、生物多様性を守ることにつながると思います。
また、飼いはじめたペットは自然に放さないこと。最期まで責任を持って、命を大切にしましょう。
自治体やボランティアが主催する自然観察会に参加するのも良いでしょう。観察結果が自治体や環境省のデータとして活用される場合もありますから、実際の保全活動にも役立ちます。


生物多様性と聞くと壮大に感じて、なかなか自分事のように思えなかったのですが、お話を聞いて私たちの生活とのつながりが見えてきました。
人間も生物多様性の連鎖のひとつに関わっていることを自覚して、自分のできることから取り組んでいきたいと思います。今日はありがとうございました。
人間も生物多様性の連鎖のひとつに関わっていることを自覚して、自分のできることから取り組んでいきたいと思います。今日はありがとうございました。

ありがとうございました。

本記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
この記事が、皆さんとともに学び、考えるきっかけとなれば幸いです。
よろしければ、あなたの大切な人や社会課題に関心のある方にも、ぜひシェアしていただけるとうれしいです。
また、以下に関連記事も公開していますので、あわせてご覧ください。
■関連記事
■関連リンク
■関連ブログ



![脱炭素社会を実現するには? [後編]](https://geoschool.pasco.co.jp/assets_c/2_kou_thumbnail_250701_3.jpg)
![脱炭素社会を実現するには? [前編]](https://geoschool.pasco.co.jp/assets_c/1_zen_thumbnail_250701.jpg)