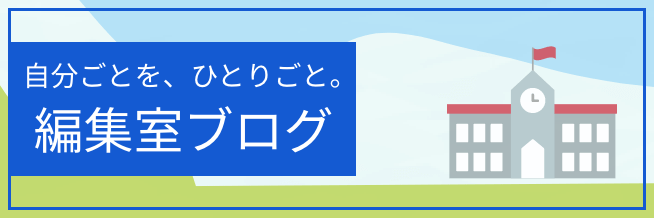編集室ブログ
文化を守り未来へつなぐ

8月29日は「文化財保護法施行記念日」です。
1949年に法隆寺金堂の壁画が火災で焼失したことをきっかけに、1950年の今日、文化財保護法が施行され、記念日として制定されました。
なぜ文化財を守るのか?
文化財は、形のあるものから形のないものまで多岐にわたり、日本の歴史・文化を理解するうえで欠かせない重要な国民的財産です。遺跡や建造物からは当時の技術や社会構造を読み解くことができ、美術工芸品からは、当時の美意識や価値観を知ることができます。また、地域のアイデンティティ、観光資源としての役割もあります。
ただ、残念なことに文化財保護法の制定後も、文化財が自然災害や火災により被害を受けた事例はあります。記憶に新しいものでは、2016年の熊本地震で熊本城の石垣や櫓(やぐら)が損壊したほか、2019年には沖縄の首里城正殿などが焼失しました。
これらは、復旧・復元に向けた作業が続けられていますが、元の姿を取り戻すには困難を極めます。だからこそ、文化財の損失は、本当に避けなければならないと思います。
文化財は“過去のもの”ではなく、“未来に残すもの”
2019年の文化財保護法改正により、従来の「保存中心」から「保存と活用の両立」へ大きく見直されました。
貴重な文化財を「守る」だけでなく「活かす」ために、私たちにできることはなんでしょうか。火気厳禁、落書き禁止などルールを守り、文化財を傷つけない行動を心がけること。文化財を観光資源として利用する一人ひとりが、その価値を認識することが非常に重要だと思います。
また、活用という観点では、世の中から文化財に関心を持ってもらう必要もあります。学校教育のなかで次世代の担い手である子供たちに文化財の価値を伝えることは、非常に重要な活動だと思います。
文化財を「守る」だけではなく「活かす」ことで地域の魅力再発見や経済にも貢献します。地域振興での活用など、社会と一体となって未来に残す努力をしていきたいですね。
(文:K.T)
■関連ページ
パスコの文化財業務支援