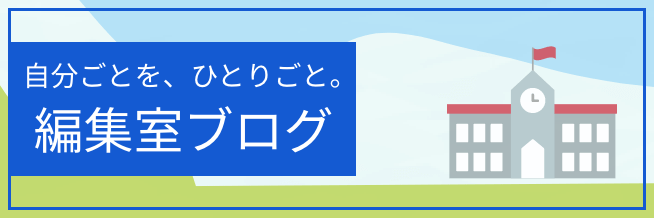編集室ブログ
鉄道の日に振り返る150年の進化

10月14日は「鉄道の日」。1872年、日本初の鉄道路線が新橋(現・汐留)~横浜(現・桜木町)間で開業したことに由来しています。
当時の所要時間は53分。江戸時代の終わりからわずか5年しか経っていない時代に、蒸気機関車が煙を吐きながら走る姿は、まさに文明開化の象徴として、人々に強烈なインパクトを与えたことでしょう。運賃も今より高めで、庶民には特別な機会にしか利用できない贅沢な移動手段だったようです。
それから150年以上が経過した現在、同じ区間をJR東海道線で移動すると、所要時間は最速で約23分、当時の半分以下の時間です。運賃は当時の10分の1まで安くなっています。早く安く移動できる鉄道は誰もが気軽に利用できる生活の足となりました。
この進化の背景には、レールや車両の改良、信号システムの高度化、電化や複線化といった日本の鉄道技術の飛躍的な発展があります。また、安全性と速度の向上を両立させるために、目に見えない部分でもたくさん工夫されています。たとえば、車両やレールの微細な変位を検知するセンシング技術や、架線や橋梁をミリ単位で監視する検査システム、これらを統合的に管理する設備管理の仕組みなどです。
こうした目に見えない努力と革新が積み重なってこそ、鉄道は「より安全に、より速く」という進化を遂げることができました。
鉄道は今や、単なる交通手段を超えて、日本の経済と社会を支える重要なインフラとなりました。そして、リニア中央新幹線の開発など、未来に向けた進化も続けています。
鉄道の日に、過去の挑戦と技術の進化を振り返りながら、未来への可能性に思いを馳せてみませんか?
(文:K.T)
画像:横浜市桜木町で保存されている、鉄道創業当時、実際に走行していた蒸気機関車(2020年撮影)