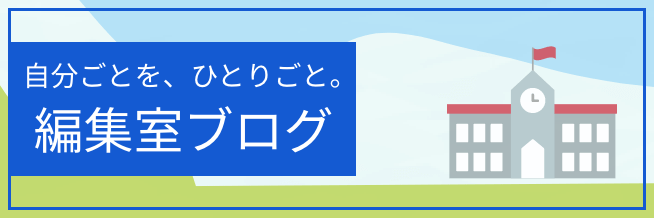編集室ブログ
新潟中越地震で振り返る、情報の重要性

2004年10月23日に、新潟県中越地方を襲った最大震度7の大地震。あの日の記憶は、私が日常生活で常に「防災」を意識するきっかけとなりました。
仕事中だった私が感じたのは、突き上げるような本震の衝撃と、その後わずか2時間の間に3回も発生した震度6以上の余震。まるで地面が唸っているようで、恐怖で身動きが取れませんでした。
しばらくして家族の安否を確認できホッとしたのも束の間、今度は車での移動が待っていました。でも道は渋滞し、ガソリンスタンドは長蛇の列。そして地震でできた亀裂のようなものもありました。車の燃料は足りる?携帯の充電は?また大きな余震がきたらどうする?と、不安は尽きません。ラジオから流れる情報に耳を傾けながら、恐怖と不安で震える手をごまかすようにハンドルを握りしめて、なんとか家にたどり着いたのを覚えています。
この地震では、地滑りや斜面崩落が発生し、多くの集落が孤立しました。そして、通信が寸断され停電した地域では、被害の全体像や状況が把握できないという課題も浮き彫りになりました。
当時、日本の携帯電話やPHSの普及率が約7割で、若年層が一人一台に突入しはじめた頃。主な情報源はラジオやテレビで、今のようにスマホでどこからでも情報収集できる時代ではありませんでした。今思えば、少ない情報を頼りに夜道を40㎞以上も移動したことに驚きます。
あれから20年以上経ちスマホが主流となった今、限られた情報のなかで不安と戦っていた頃からずいぶん変わったと実感します。
災害情報アプリでは速報や情報が通知で届き、SNSではリアルタイムで様子が伝わり、情報が「多く」「速く」「見える」ようになりました。こうしたツールは、情報の孤立を防ぎ冷静な判断と行動を後押ししてくれます。
いざという時に自分の命を守るために。技術の進化に感謝しながら、これからも防災対策を続けていきたいと思います。
(文:S.H)